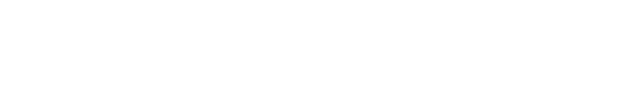むくみ改善のセルフケアと医師相談が必要なサインとは?
むくみが続いて不安な方へ
夕方になると足がパンパンに腫れる、靴下の跡がくっきり残る…。こうした「むくみ」は多くの方が経験する症状です。とくに立ち仕事や長時間のデスクワークをしている方にとっては日常的な悩みといえるでしょう。
一方で、むくみが長引いたり片足だけに出たりする場合は、体の異常を知らせるサインである可能性もあります。
本記事では【むくみ 改善】に役立つセルフケアの方法と、医師に相談すべき危険なサインについて、厚生労働省や日本循環器学会などのガイドラインを踏まえて解説します。
江東区東陽町・木場駅周辺でむくみにお悩みの方が、安心して受診につなげられる情報をお届けします。
むくみ 改善の基本解説
なぜむくみが起こるのか
むくみ(浮腫)は、血管から水分が過剰に漏れ出し、皮下組織にたまることで生じます。原因は大きく二つに分けられます。
-
生理的なむくみ:立ちっぱなし、塩分過多、アルコール摂取、ホルモンバランスの変化などによる一時的なもの。
-
病的なむくみ:心不全、腎疾患、肝疾患、深部静脈血栓症など病気が背景にあるもの。
特に「片足だけが急にむくんだ」「むくみと同時に息苦しさや動悸がある」場合は、病的なむくみの可能性があり注意が必要です。
生活や健康に与える影響
軽度のむくみでも、足が重く感じたり、歩行や睡眠の質に影響を与えます。慢性的に続けば、日常生活の質(QOL)低下につながりかねません。さらに心臓・腎臓・肝臓の病気が隠れていることもあり、早めの対処が重要です。
むくみ 改善・予防の仕組み
血液と水分のメカニズム
心臓から送り出された血液は動脈を通って全身に行き渡り、老廃物を含んだ血液は静脈を通じて心臓に戻ります。ふくらはぎの筋肉はこの血流を押し上げるポンプの役割を果たしており、比喩的に「第二の心臓」と呼ばれることもあります。筋肉の収縮が弱いと、下肢に水分がたまりやすくなり、むくみが起きます。
国内外ガイドラインの推奨事項
-
WHO:塩分摂取を1日5g未満に抑えることを推奨。
-
日本高血圧学会:高血圧管理のために減塩(6g未満/日)が推奨されており、体の水分バランス改善に寄与する可能性がある。
-
日本腎臓学会:腎疾患患者では食事療法として減塩が重要とされ、むくみ予防にも関連。
日本腎臓学会CKD診療ガイドライン
このように「塩分制限」「適度な運動」「水分バランス調整」は国際的にも推奨されている改善策です。
むくみ 改善に効果的なセルフケア方法
日常生活でできる具体的な方法
-
減塩食の実践
加工食品・インスタント食品を控え、出汁や香辛料で味を補う工夫をしましょう。カリウムを多く含む食品(例:バナナ1本、ほうれん草のおひたし1皿、アボカド半分程度)を毎日の食事に取り入れると、余分なナトリウム排出を助けます。 -
こまめな運動
1日20〜30分のウォーキングや階段の昇降は下肢の血流改善に有効です。デスクワーク中も1時間に1回は立ち上がり、ふくらはぎを伸ばす習慣をつけましょう。 -
足を高くして休む
就寝時に足を心臓より少し高くして横になることで、血液やリンパの流れが改善されます。
むくみが腎臓や心臓の病気に関連する場合もあります。詳しくは当院の腎臓内科ページもご確認ください。
補助的な方法
-
着圧ソックスの使用:下肢静脈の血流をサポート。医療用と市販用があり、症状に応じて選びましょう。
-
水分摂取の工夫:むくみがあるからといって水分を極端に制限するのは逆効果。1日1.5〜2ℓを目安にバランスよく摂取しましょう。
-
生活習慣の改善:アルコールの過剰摂取を控え、睡眠をしっかりとることも大切です。
むくみ 改善に必要な運動強度・時間帯・頻度
運動の目安
-
有酸素運動は週3〜5回、1回30分程度が目安。
-
ストレッチや下肢の屈伸運動は寝る前に5〜10分取り入れると効果的です。
年齢・性別・既往症ごとの注意
-
高齢者:転倒リスクを避け、無理のない歩行や椅子に座ってできる運動を推奨。
-
女性:ホルモンの影響で生理周期に伴いむくみやすい時期があるため、セルフケアを継続して行うことが大切。
-
心疾患や腎疾患の既往がある方:運動や水分摂取については必ず主治医に確認を。
むくみ 改善の注意点と医師に相談すべきケース
危険なサイン
-
片足だけ急にむくんだ(深部静脈血栓症の可能性)
-
息苦しさ・胸の痛みを伴う(心不全・肺塞栓症のリスク)
-
皮膚や白目が黄色っぽくなった(肝機能障害のサイン)
-
顔やまぶたがむくむ(腎疾患やネフローゼ症候群の可能性)
医師相談が必要なケース
-
むくみが2週間以上続く
-
むくみとともに体重が急激に増加
-
薬を飲み始めてからむくみが悪化した場合(降圧薬やホルモン薬などが原因となることがあります)
これらに該当する場合は、自己判断せず早めに医療機関を受診しましょう。
江東区・東陽町・木場駅周辺でむくみ改善を相談したい方へ
江東区・東陽町・木場駅周辺にお住まいで「むくみ 改善」を希望される方は、当院の内科・腎臓内科外来でご相談いただけます。
地域に根ざした医療機関として、生活習慣のアドバイスから必要な検査・治療まで一貫してサポートいたします。
予約方法:電話・Web予約可能です
まとめ
-
むくみは「一時的な生活習慣によるもの」と「病気が背景にあるもの」に分かれる。
-
むくみ 改善には「減塩・運動・水分バランス」が基本。
-
片足だけのむくみや息苦しさを伴う場合は、深刻な病気のサインである可能性がある。
-
江東区・東陽町・木場駅周辺で不安を感じたら、早めに医療機関へ相談することが大切。
「ただのむくみ」と思っていても、体のSOSであることがあります。セルフケアと医療機関のサポートをうまく組み合わせて、健康な毎日を送りましょう。
記事執筆者
第二服部医院 院長 宮内 隆政
略歴
- 平成21年 東邦大学医学部医学科 卒業
- 平成21年〜 東邦大学医療センター佐倉病院
- 平成23年〜 東邦大学医療センター 腎臓内科(都立墨東病院救急・救命センター、国立病院機構東京病院 呼吸器科で研修)
- 平成24年〜 東京ベイ浦安市川医療センター 総合内科
- 平成26年〜 東京ベイ浦安市川医療センター 腎臓・糖尿病内分泌科
- 平成27年〜 聖路加国際病院 腎臓内科
- 平成30年〜 Cedars Sinai Medical Center
- 令和1年〜令和2年 ユアクリニック秋葉原
- 令和1年〜 聖マリアンナ医科大学病院 腎臓高血圧内科 登録医
所属学会
日本内科学会、日本プライマリケア学会、日本腎臓学会、日本透析医学会、日本臨床腎移植学会、日本高血圧学会、外来小児科学会、米国内科学会、米国腎臓学会、国際腎臓学会
資格
- 総合内科専門医
- 腎臓専門医
- 透析専門医
- 日本プライマリケア学会認定医