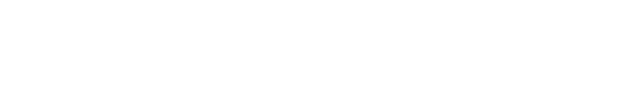腎臓病の原因になる「塩分過多」―毎日の食事で注意すべきポイント
はじめに
「味の濃いものが好き」「外食が多い」――そんな日常の積み重ねが、知らず知らずのうちに腎臓に負担をかけているかもしれません。
腎臓は体の中で余分な塩分や老廃物を排出する重要な臓器ですが、塩分を摂りすぎるとその働きが鈍り、やがて慢性腎臓病(CKD)へと進行することがあります。
本記事では、「塩分過多」が腎臓病の原因になる理由と、毎日の食事で気をつけたい注意点・減塩方法について、腎臓内科の視点からわかりやすく解説します。
なぜ塩分の摂りすぎが腎臓に悪いのか?
腎臓は、血液中の水分やナトリウム(塩分の主成分)のバランスを調整し、体内の“塩分濃度”を一定に保つ働きをしています。
しかし、食事で塩分を摂りすぎると、体内のナトリウム濃度が高まり、腎臓はそれを排出するために余分な水分を溜め込みます。その結果、血液量が増加し、血圧が上昇します。
高血圧の状態が続くと、腎臓内の細い血管(糸球体)に強い圧力がかかり、徐々にダメージを受けていきます。これが高血圧性腎障害と呼ばれる状態で、慢性腎臓病の大きな原因の一つです。
また、腎臓の機能が低下すると、ナトリウムや老廃物がさらに体内に蓄積し、むくみや倦怠感などの症状が現れる悪循環に陥ります。
腎臓病は自覚症状が出にくい「沈黙の病気」と呼ばれています。気づいたときには進行していることも多く、日々の塩分摂取を意識的にコントロールすることが何より重要です。
知らないうちに“塩分過多”になっている日常の落とし穴
「しょっぱい味が好き」という自覚がなくても、現代の食生活では無意識のうちに塩分過多になりがちです。
たとえば、次のような食品には多くの塩分が含まれています。
-
カップ麺・インスタントスープ:1食あたり約5〜6g
-
漬物・梅干し:1個で約1〜2g
-
ハム・ベーコンなどの加工食品:1枚あたり約0.5〜1g
-
外食の定食メニュー:1食で7〜8gを超えることも
日本人の平均的な塩分摂取量は1日10〜11g程度とされており、厚生労働省が推奨する1日6g未満を大きく上回っています。
特に「汁物を飲み干す」「ドレッシングを多く使う」といった習慣も、気づかないうちにナトリウム過剰につながります。
塩分過多は単に血圧を上げるだけでなく、腎臓への直接的な負担を増やす要因です。体の“塩分処理能力”を超える食生活が続くと、腎臓の働きが徐々に低下していくことを覚えておきましょう。
腎臓を守るための塩分摂取の目安
腎臓を守るには、まず1日あたりの塩分摂取量を意識することが大切です。
厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、成人男性で1日7.5g未満、成人女性で6.5g未満が目標値とされています。
さらに、腎臓病や高血圧を指摘された方は6g未満を目指すのが理想です。
なお、「塩分を減らしすぎると体に悪いのでは?」という疑問もありますが、通常の食事をしている限り欠乏することはほぼありません。
大切なのは“極端に減らす”のではなく、継続して適正な量を維持することです。
また、水分摂取も腎臓の働きを助けます。水やお茶をこまめに飲むことで、体内の老廃物や余分な塩分を排出しやすくなります。
ただし、心臓病や腎不全のある方は水分制限が必要な場合もあるため、医師に相談して調整しましょう。
今日からできる“減塩”の実践ポイント
「減塩」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、調味料や調理法を少し工夫するだけで塩分は大きく減らせます。
味つけの工夫
-
だし・酸味・香辛料を活用して、薄味でも満足感をアップ
-
レモン・お酢・こしょう・ごまなどで風味を強調
-
甘辛よりも“うま味+酸味”のバランスを意識
調味料の使い方
-
しょうゆやソースは「かける」ではなく「つける」
-
減塩タイプの調味料を選ぶ
-
味見をしてから足す習慣をつける
食材選びと外食時の工夫
-
加工食品よりも生鮮食材を選ぶ
-
汁物のスープは全部飲まない
-
ドレッシングは別添えにして量を調整
このような小さな工夫の積み重ねが、腎臓を守る第一歩です。
特に「むくみ」「倦怠感」「尿の泡立ち」が気になる場合は、塩分摂取を見直すサインと考えてください。
腎臓にやさしい生活習慣もセットで意識を
塩分を控えるだけでなく、腎臓にやさしい生活習慣を整えることも重要です。
-
十分な睡眠とストレス管理で血圧を安定させる
- 軽い運動(ウォーキングなど)で代謝と循環を改善
-
アルコールや喫煙を控えることで血管の健康を保つ
また、年に1回は健康診断でクレアチニン値やeGFR(推算糸球体濾過量)を確認しましょう。
これらは腎臓機能の指標であり、早期に異常を発見できれば進行を防ぐ治療や食事指導が可能です。
当院の「腎臓内科」についてはこちら
まとめ ― 「塩分を控えること」が腎臓を守る第一歩
腎臓病は自覚症状が出にくいからこそ、日常の食事での予防が何よりも大切です。
塩分を意識的に控えることで、血圧や腎臓の負担を減らし、将来的な透析リスクを下げることができます。
「塩分過多かも?」と思ったら、食事を見直すだけでなく、早めに腎臓内科を受診しましょう。
当院の腎臓内科について
当院では、生活習慣による腎臓の負担を軽減するための検査・食事指導・薬物療法を総合的に行っています。
血圧やクレアチニン値が高めの方、むくみや疲れを感じる方は、ぜひ一度ご相談ください。
早期の対応が、将来の腎臓を守る最大の鍵です。
記事執筆者
第二服部医院 院長 宮内 隆政
略歴
- 平成21年 東邦大学医学部医学科 卒業
- 平成21年〜 東邦大学医療センター佐倉病院
- 平成23年〜 東邦大学医療センター 腎臓内科(都立墨東病院救急・救命センター、国立病院機構東京病院 呼吸器科で研修)
- 平成24年〜 東京ベイ浦安市川医療センター 総合内科
- 平成26年〜 東京ベイ浦安市川医療センター 腎臓・糖尿病内分泌科
- 平成27年〜 聖路加国際病院 腎臓内科
- 平成30年〜 Cedars Sinai Medical Center
- 令和1年〜令和2年 ユアクリニック秋葉原
- 令和1年〜 聖マリアンナ医科大学病院 腎臓高血圧内科 登録医
所属学会
日本内科学会、日本プライマリケア学会、日本腎臓学会、日本透析医学会、日本臨床腎移植学会、日本高血圧学会、外来小児科学会、米国内科学会、米国腎臓学会、国際腎臓学会
資格
- 総合内科専門医
- 腎臓専門医
- 透析専門医
- 日本プライマリケア学会認定医